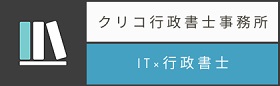古物商許可申請
最安で全国対応【法人・個人】
全ての書類が「リモート」で完成します。
書類作成、警察との打ち合わせも代行します。

こんなことをしたい方は、
古物商許可が必要です。
- メルカリ、ヤフオクなどで古物を転売
- せどり
- フリーマーケット(古物を仕入れて販売する等)
- 中古車・中古バイク販売
- ブランド品の買取・販売
- 古書店
- リサイクルショップ
- 金券ショップ
- 古着屋
- 中古パソコンショップ
- レンタル事業
- 古物の委託販売で手数料を得る
- 古物を海外へ転売
- これらをインターネット販売する場合も許可が必要です
必要書類の一例
- 法人の登記事項証明書(法人履歴事項全部証明書)
- 法人の定款
- 住民票
- 身分証明書
- 略歴書
- 誓約書
- 賃貸借契約書のコピー
- 駐車場等保管場所の賃貸
- 借契約書のコピー
- 古物市場規約(古物市場主許可申請時のみ)
- 古物市場の参集者名(古物市場主許可申請時のみ)
- 参集者名簿に掲載されている古物商全員の許可証のコピー(古物市場主許可申請時のみ)
- 委任状
- URL届出の疎明資料
クリコ行政書士事務所にご依頼いただくメリット
① 早い ② 確実 ③ 安心 です。
クリコ行政書士事務所
古物商許可に関する価格表
変更届出・書換申請
代行プラン-
全国対応
-
完成済み書類一式を郵送
-
完全リモート
-
警察への事前相談
-
お電話やメールでのサポート
書類作成おまかせ
代行プラン-
全国対応
-
役員1名分の書類取得費用込み
-
完成済み書類一式を郵送
-
完全リモート
-
警察への事前打ち合わせ
-
職権による必要書類の収集
-
お電話やメールでのサポート
書類作成+申請おまかせ
代行プラン-
群馬県、近県の一部
-
役員1名分の書類取得費用込み
-
申請の代行業務
-
完全リモート
-
警察への事前打ち合わせ
-
職権による必要書類の収集
-
お電話やメールでのサポート
※ 申請には「収入証紙代」 19,000円(法定費用)が別途必要です。
※ 法人役員が2名以上の場合、必要書類の収集代行 1名につき 5,000円(税別)が必要です。
※ 交通費やその他の実費が必要な場合など、お見積りでご確認ください。
許可証交付までの流れ
まずは お問い合わせフォーム から、ご相談ください。
お見積りを確認の上、ご依頼の方は金額をお振込みいただきます。
当事務所でお振込み確認し次第、書類作成に着手いたします。
完成された書類一式を、警察署へ提出するだけです。
申請まで代行するプランは、お待ちいただくだけです。
警察署が許可をだすまでの標準処理期間は 40日(目安)です。
古物商許可証が発給され、晴れて営業となります。
おめでとうございます。
ご注意していただく事項
- まずは「お問合せフォーム」よりご連絡いただき、詳細をヒアリングいたしますので、お見積もりをご覧になってご検討ください。
お問い合わせフォーム
* の付いている項目は入力必須です
よくあるご質問 FAQ
個人事業で許可を受けていた方が、事業を法人化した場合、取得済みの許可変更ということではなく、法人の古物商許可を取り直すことが必要となります。
共同名義人の方に「使用許可」を書面でいただく必要があります。
所有者の方に古物営業の「使用許可」を書面でいただく必要があります。
法令関係のご質問 FAQ
「古物営業法」の目的は、古物の売買などその流通に関して、盗品等の犯罪被害品が混入する可能性があります。
そのため法で定められた各種義務を守ることにより、窃盗などの犯罪の防止を図り、併せて被害が迅速に回復できる社会を維持していこうということを目的としています。
- 一度使用された物品
- 使用されない物品で使用のために取引されたもの
- これらいずれかの物品に「幾分の手入れ」をしたもの
「使用」とは、その物本来の目的にしたがってこれを「使う」ことをいいます。(例:衣類→着用、自動車→運行、カメラ→撮影)
また、「幾分の手入れ」とは、物の本来の性質、用途に変化を及ぼさない形で、修理等を行うことをいいます。
古物(物品)は、13品目に分類され、営業所ごとに取り扱う品目を定めて申請(届出)します。
美術品類 | 書画、彫刻、工芸品等 |
|---|---|
衣類 | 和服類、洋服類、その他の衣料品 |
時計・宝飾品類 | 時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等 |
自動車 | その部分品を含みます。 |
自動二輪車及び原動機付自転車 | これらの部分品を含みます。 |
自転車類 | その部分品を含みます。 |
写真機類 | 写真機、光学器等 |
事務機器類 | レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等 |
機械工具類 | 電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等 |
道具類 | 家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物等 |
皮革・ゴム製品類 | カバン、靴等 |
書籍 | |
金券類 | 商品券、乗車券、郵便切手及びこれらに類する証票その他の物として古物営業法施行令第1条に定められているもの |
大型機械類のうち
- 総トン数が20トン以上の船舶
- 航空機
- 鉄道車両
- 重量が1トンを超える機械で、土地又は建造物にコンクリートや溶接等で固定し、簡単に取り外しができないもの
- 重量が5トンを超える機械(船舶を除く。)であって、自走及びけん引したりすることができないもの
これらは盗品として売買される可能性が低いため、法の規制から除外されています。
「古物営業」とは、次の三つの営業をいいます。
- 古物商が、公安委員会から許可を受けて、古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業
- 古物市場主が、公安委員会から許可を受けて、古物市場(古物商間の古物の売買又は交換のための市場をいい、通常はオークションのような競り売りの方法で行われる。)を経営する営業
※古物市場での取り引きは、古物商に限られていますので、一般の方は参加できません。 - 古物競りあっせん業者が、公安委員会に届け出て、いわゆるインターネットオークションのように古物を売買しようとする者のあっせんをホームページを使用する競りの方法により行う営業で、インターネットオークションの運営者がこれにあたります。
許可を受けようとする方が、次に該当する場合には、許可を受けられません(欠格事由)。
また、既に許可を受けている者が次に該当した場合は、許可の取り消しの対象となります。
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 禁錮以上の刑に処せられ、又は一定の犯罪(注1)により罰金の刑に処せられて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
- 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で、古物営業法施行規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者(注2)
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して3年を経過しないもの(注3)
- 住居の定まらない者
- 古物営業法第24条第1項の規定により、古物営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
- 古物営業法第24条第2項の規定により、許可の取り消しに係る聴聞の期日等の公示の日から、取り消し等の決定をする日までの間に、許可証を返納した者で、当該返納の日から起算して5年を経過しない者
- 心身の故障により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施することができない者として古物営業法施行規則で定めるもの
- 営業について成年者と同一の能力を有しない未成年者(注4)
- 営業所又は古物市場ごとに、業務を適正に実施するための責任者としての管理者を選任すると認められないことについて相当な理由のある者(注5)
- 法人の役員が前記1.から8.までに掲げる事項に該当するとき。
注1 一定の犯罪…古物営業法第31条に規定する罪(無許可、不正手段による許可取得、名義貸し、営業停止処分中の営業)、刑法第235条(窃盗)、刑法第247条(背任)、刑法第254条(遺失物横領)、刑法第256条第2項(盗品等運搬、保管、有償譲受け又は有償処分のあっせん)
注2 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者、暴力団以外の犯罪組織の構成員で、当該組織の性格により、強いぐ犯性が認められる者等が該当します。
注3 暴力団員による不当な行為等に関する法律により公安委員会から命令又は指示を受けてから3年を経過しないもの
注4 婚姻している者、古物商の相続人であって法定代理人が欠格事由に該当しない場合は申請できます。
注5 欠格事由に該当している者を管理者としている場合などが該当します。
次に該当する方は、許可を取り消される場合があります。
- 偽りその他不正な手段により許可を受けた。
- 欠格事由に(上記「許可を受けられない場合」参照。ただし、9を除く。)に該当する。
- 許可を受けてから6月以内に営業を開始しない、又は引き続き6月以上営業を休止し、現に営業を営んでいない。
- 古物商等の営業所若しくは古物市場の所在地が確認できないとき又は古物商等の所在(法人の場合は、役員の所在)が確認できないときに、公安委員会がその事実を官報に公告し、その公告の日から30日を経過しても申出がない場合
また、上記のほか、古物営業法に違反したり、この法律に基づく命令や処分に違反したり、古物営業に関し他の法令の規定に違反すると、許可を取り消されたり、6月を超えない範囲内で期間を定めて、古物営業の停止を命ぜられることがあります(法第23条、第24条)。
催物場への出店など、自身の営業所の外で古物営業を行う場合を「行商」といいます。「古物市場に出入りして取引を行う」、「取引の相手方の住所に赴いて取引する」、「デパート等の催事場に出店する」場合などは、許可内容が「行商する」となっていることが必要です。
「行商する」になっていても、古物を買い受ける場合は、場所に制限があります(法14条第1項)。古物商以外の一般の方(法人を含む。)から古物を「受け取る」ことは「自身の営業所」若しくは「相手方の住所又は居所」でなければなりません。ただし、仮設店舗営業の届出をすれば仮設店舗で古物を受け取ることは可能です。
https://www.pref.aichi.jp/police/shinsei/sonota/kobutsu/kobutukaisetu.html
「標識」は、古物営業法施行規則第11条、別記様式第13条に様式が定められています。(各署の古物商防犯協力会でも斡旋しています)。

- 材質は、金属、プラスチック又はこれらと同程度の耐久性を有するものとしてください。
金属板、プラスチック板と同等のもの。紙ベースのものは不可。 - 色は、紺色地に白文字としてください。
表示内容が容易に改変できないもの。
紙に印字してプラスチック板に貼り付けるだけでは不可。 - 番号は12桁の許可証の番号を入れてください。
- 大きさは、縦8センチメートル、横16センチメートルです。
- 「○○○商」の「○○○」部分には、当該営業所又は仮設店舗において取り扱う古物に係る第2条各号に定める区分(二以上の区分に係る古物を取り扱う場合は、主として取り扱う古物に係る部分)を記載してください。
間違った表示の標識を販売している業者もありますので、注意してください。
https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/smph/tetsuzuki/kobutsu/youshiki/hyoshiki.html
「行商従業者証」は、古物営業法施行規則第10条、別記様式第12号で様式が定められています。

表

裏
- 材質は、プラスチック又はこれらと同程度の耐久性を有するものとしてください。
- 大きさは、縦5.5センチメートル、横8.5センチメートルです。
- 表面の「氏名」、「生年月日」欄には、行商をする当該従業員の氏名及び生年月日を記載してください。
- 「写真」欄には、行商をする当該従業員の写真(縦2.5センチメートル以上、横2センチメートル以上のもの)を貼り付けてください。
- 裏面は、許可内容を記載します。許可証をよく確認して間違いのないように作成してください。
「古物商の氏名又は名称」欄には、
個人許可の場合は、氏名、
法人許可の場合は、法人の正式名称
古物商の住所又は居所」欄には、
個人許可の場合は、許可者の住所、
法人許可の場合は、法人の住所(営業所の住所ではありません)
「許可番号」欄には、「公安委員会名」、「許可番号」
「主として取り扱う古物の区分」欄には、届け出ている主品目
を記載してください。
https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/smph/tetsuzuki/kobutsu/youshiki/gyosho.html
「帳簿」は、古物営業法施行規則第17条、別記様式第15号及び別記様式第16号に様式が定められています。
古物商が記載する帳簿の様式

備考
- 「受入れ」の「区別」欄には買受け又は委託の別を記載し、「払出し」の「区別」欄には売却、委託に基づく引渡し又は返還の別を記載すること。
- 「品目」欄は、一品ごとに記載すること。
- 「特徴」欄には、例えば、衣類にあっては「上衣、シングル、鈴木のネーム入り、チョッキ、ねずみ色裏付き、ズボン、後ポケットふたなし」、時計にあっては「オメガ、何型、何番、文字板に傷あり」のように記載し、自動車にあっては自動車検査証に記載された自動車登録番号又は車両番号、車名、車台番号及び所有者の氏名又は名称等の必要な事項を記載すること。
- 現に使用している帳簿に既に住所、氏名、職業及び年齢が記載してある者については、氏名以外の事項で異動のないものの記載は、省略することができる。
古物市場主が記載する帳簿の様式

備考
- 「品目」欄は、一品ごとに記載することとし、同欄には、例えば、「紺サージ背広三つぞろい」、「金側腕時計」、「黒色軽自動車」のように、品名を記載すること。ただし、同一種類の製品で、区別しにくいものは、一括して記載することができる。
- 「特徴」欄には、例えば、衣類にあっては「上衣、シングル、鈴木のネーム入り、チョッキ、ねずみ色裏付き、ズボン、後ポケットふたなし」、時計にあっては「オメガ、何型、何番、文字板に傷あり」のように記載し、自動車にあっては自動車検査証に記載された自動車登録番号又は車両番号、車名、車台番号及び所有者の氏名又は名称等の必要な事項を記載すること。
https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/smph/tetsuzuki/kobutsu/youshiki/chobo_yoshiki.html